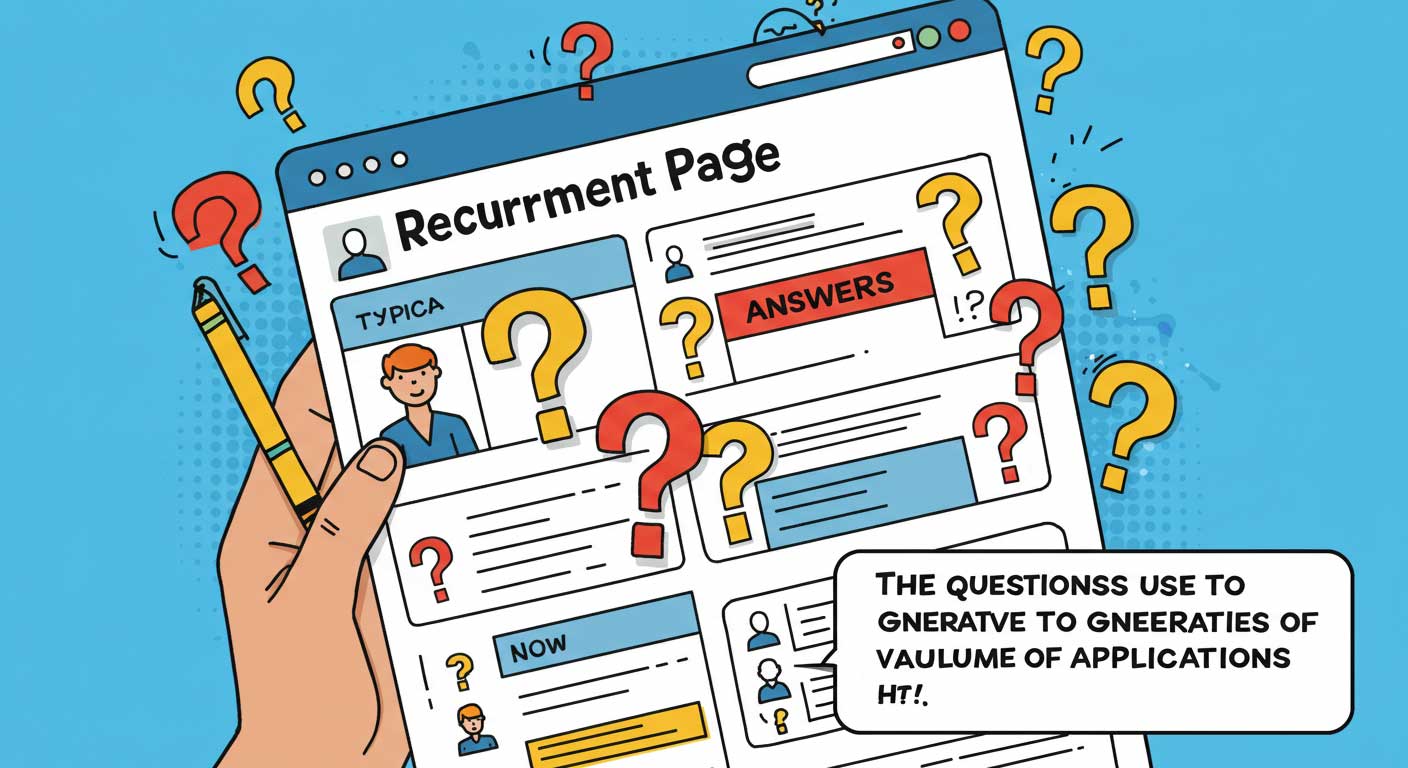「うちは未経験OKです」では、人は動かない──採用に必要なのは“問い”だった
第1章:採用ページに「正解」を書いていないか?
多くの採用ページが、まるで就職試験の「模範解答集」のように見える。
企業理念、求める人物像、社風、待遇、制度──。ありとあらゆる“答え”が最初から書かれており、応募者はそれを読みながら「この企業に自分が合っているかどうか」を、自ら判断する。
だが、考えてみてほしい。
“すべてを先に語ってしまう採用ページ”は、本当に人を惹きつけているだろうか?
実は、すでにすべてが書かれているページほど、人は興味を持ちづらい。
それは、あたかもネタバレされた映画のようなものだ。結末までわかっている物語に、人は最後まで付き合ってくれない。
第2章:「答え」ではなく「問い」が人を動かす
人間は、「完成されたもの」ではなく「解き明かすべきもの」に惹かれる。
恋愛における“駆け引き”、推理小説における“伏線”、テレビCMにおける“謎の演出”──そのすべてが「問い」を提示している。
採用も、実はこれと同じ構造を持っている。
「うちは〇〇な会社です」「〇〇な人を求めています」──こうした答えを先に語ってしまうよりも、
「あなたは、どんな未来をこの会社で描きますか?」
「『働く』とは、あなたにとってどんな行為ですか?」
「なぜ、あなたは“変わりたい”と思ったのですか?」
といった“問い”の形で届けることで、人は自らの思考を動かし始める。
そしてこの“思考のスタート地点”こそが、応募というアクションの引き金になる。
第3章:採用コピーの黄金律「問いが共感を呼ぶ」
求人コピーには、大きく分けて二種類ある。
- 「答え型コピー」:うちは◯◯な職場です。未経験歓迎。アットホーム。安定企業。
- 「問い型コピー」:あなたが“働く意味”を感じたのは、いつですか?
前者は情報を伝えるが、後者は感情を呼び起こす。
ここでいう「問い」とは、単なるクイズではない。読む人に“自分ごと化”させる装置だ。思考を内側に向かわせることで、心の中に小さな“共鳴”を起こす。
ある警備会社の採用LPでは、トップにこう書かれていた。
「あなたが“誰かの安心”を守った日は、ありますか?」
この問いは、読者の中にある経験や感情を探らせ、そして「この会社でなら、それができるかもしれない」と思わせる。
問いは、共感を喚起するためのトリガーなのだ。
第4章:「問い」をデザインする方法
「問いを活用したい」と思っても、どのように設計すればよいのか。
以下に、実際の構成技術を紹介しよう。
1. 自問型
読者自身に語りかけるタイプ。
- 「あなたが最後に“やりがい”を感じた仕事は何ですか?」
- 「今の職場で、5年後も笑っていられますか?」
2. 過去喚起型
読者の“記憶”に訴える。
- 「子どもの頃、“ヒーロー”になりたいと思ったことはありませんか?」
- 「学生時代、どんなチームでどんな役割を担っていましたか?」
3. 逆説型
固定観念に一石を投じる。
- 「本当に、“安定”だけが正解ですか?」
- 「“未経験だから無理”と決めつけていませんか?」
4. 社会接続型
社会的課題と読者を接続する。
- 「介護の現場で、“人手不足”を実感したことはありますか?」
- 「誰かの“最期”に、立ち会ったことはありますか?」
特に医療・介護・福祉分野で強く作用する問いだ。
第5章:AI時代だからこそ、「問い」の力が活きる
採用市場は今、AIによる自動化が進み、「答え」は大量に生成される時代になった。
AIは企業情報をまとめ、条件を整形し、求人票の形式に落とし込む。
だが、「問いを生む力」だけは、いまだ人間の領域だ。
「なぜあなたは働くのか?」
「誰のために働きたいのか?」
「自分を変えるとは、どういうことか?」
これらは、データ処理では導き出せない。人間の経験と感情が織りなす、“文脈の中の問い”である。
だからこそ、採用の現場にはまだ、人間が人間に問いを投げかける構造が必要なのだ。
第6章:「問い」は“スクリーニング”ではなく“共創”である
ここまでの話を、誤って理解してほしくない。
「問い」を使うといっても、それは“選別”のためではない。
「あなたにはこの会社に向いていない」と、問いでフィルターをかけるのではなく、
「あなたとこの職場が、どんな未来を一緒に創れるか」
「この仕事を通じて、あなたのどんな感情が動くか」
といった、“共創のスタンス”で問いを発することが重要だ。
問いとは、拒絶ではない。対話の入り口である。
第7章:「問い」のデザインが差別化を生む
求人倍率が高くなればなるほど、他社との差別化は難しくなる。
そのとき、求人内容、待遇、職種名での差は、すでに限界に近い。
だが、「問い」で差別化することはできる。
ある美容室の求人ページには、こう書かれていた。
「あなたは、誰かの“自信”をつくったことがありますか?」
この一文に、“ただ髪を切る”以上のストーリーがにじむ。
そして、それに共鳴した応募者がやってくる──この構造こそが、ブランドを作る。
答えはコピーできるが、問いはコピーできない。
だからこそ、問いこそが採用ページの差別化の核心なのだ。
第8章:まとめ──問いこそが、未来を引き寄せる
採用活動において、「すべてを説明し尽くす」ことは、むしろ応募者を遠ざける行為になりうる。
“問い”は、応募者に思考の余白を残す。
“問い”は、自分の物語として採用を捉えさせる。
“問い”は、人を動かす起点になる。
いま、企業の採用ページに求められているのは、「答えの集積」ではない。
未来を一緒に考える“問いの提示”なのだ。